近年、深刻化する人手不足を背景に、外国人材の受け入れを検討する介護・外食・建設業界などの事業者が増えています。そうした流れの中で、「特定技能」という言葉を耳にする機会もずいぶん増えました。
特定技能制度は、「初期費用が抑えられる」「即戦力として期待できる」といった点から魅力的に映る一方で、実際に運用を始めてから思わぬ課題に直面するケースも少なくありません。特定技能だけに頼ることのリスクを理解し、外国人材の“長期的な定着”を見据えた受け入れ方針を立てることが、今後ますます重要になっていきます。
本記事では、「技能実習から特定技能へと段階的にステップアップさせる」という手法に注目し、その意義やメリットについて詳しくご紹介します。
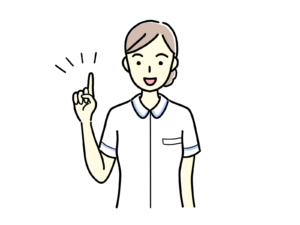
■ 特定技能の意外な落とし穴──“自由な転職”がもたらす不安定さ
特定技能制度の大きな特徴の一つに、「転職が可能」という点があります。技能実習制度では原則として転職が認められていませんが、特定技能では一定の条件を満たすことで他の企業や施設への転職が制度上可能となっています。
この自由度は、外国人労働者にとっての権利の保護という観点では重要な進歩といえますが、受け入れる側にとっては必ずしもメリットばかりではありません。
現場では、「ようやく現場の業務に慣れてきたと思ったら退職してしまった」「採用からわずか数か月で他施設に転職してしまった」という声も多く聞かれます。特に、採用直後の慣れない時期に辞められてしまうと、教育にかけた時間やコストがすべて無駄になるばかりか、現場スタッフにさらなる負担がのしかかることになります。
特定技能が“即戦力”として期待される一方で、こうした人材の流動性の高さが、長期的な定着の妨げになるという現実は、事前に十分理解しておくべきポイントです。

■ 技能実習からスタートすることで高まる「定着率」
このような課題に対し、有効な対策となり得るのが「技能実習から受け入れる」というアプローチです。技能実習制度では、原則として3年間の実習期間が設けられており、その間に以下のような“基礎づくり”が可能になります。
-
日本語の基本的な会話力や専門用語を習得
-
現場の業務内容や手順に慣れる
-
日本の生活文化・ルールを理解する
-
スタッフや利用者との信頼関係を築く
この3年間は、単なる労働力としてではなく、「将来を見据えた人材育成の期間」として捉えることができます。そして、技能実習の期間を終えた人材が、そのまま特定技能へと移行することで、すでに職場環境や業務内容を熟知しており、さらに意欲も高い状態で即戦力となってくれるのです。
特定技能単独の採用に比べ、「定着力」と「信頼性」の両面において格段に優れた人材が育つという点は、非常に大きな魅力です。

■ 「育成就労」へと制度も進化──国の方針も段階的受け入れを重視
2024年には、これまでの技能実習制度を見直す形で、新たに「育成就労」という制度がスタートしました。この制度は、単なる“労働力の確保”ではなく、外国人材の段階的なキャリア形成や定着支援を重視する点が特徴です。
育成就労の導入によって、より柔軟で現実的な外国人材の受け入れが可能になりつつあり、いきなり特定技能で採用するのではなく、「まずは育成就労から始めて、しっかり育ててから特定技能へ移行する」という考え方が、国としても推奨される方向となっています。
これは事業者にとっても、長期的に安定した人材を確保する上での大きな後押しとなるでしょう。
■ まとめ
短期的な戦力確保という視点では、特定技能制度は確かに魅力的です。しかし、現場を支える本当の力は、“人を育てる姿勢”の中にあります。
「育てる」「信頼を築く」「キャリアを支える」というプロセスを重ねた外国人材こそが、チームの一員として長く活躍し、現場の安定と成長に貢献してくれる存在になります。
JMCCでは、技能実習から特定技能へのスムーズな移行を実現するための、制度面・教育面でのサポートを行っています。「即戦力」ではなく「長期的な戦力」を育てたいとお考えの施設様は、ぜひ一度ご相談ください。

